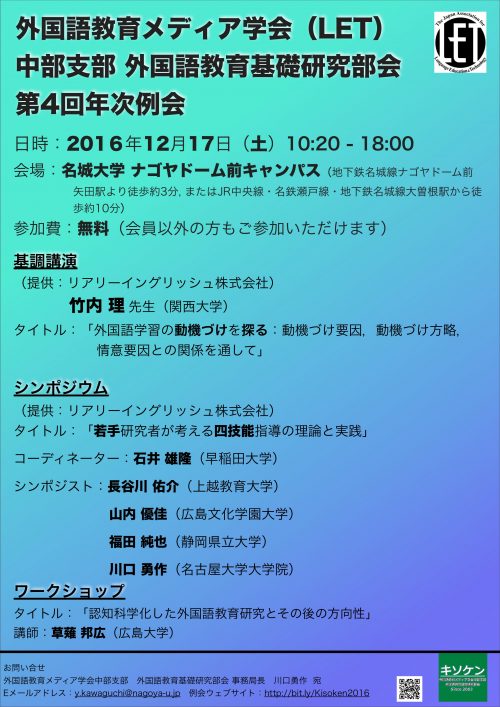主にMの学生向けです。新入生も入ってきたりする時期で,どんな研究をしたいかという話をする機会が最近多いですが,なんかそれよくわからないなと思うので少しだけ。
タイトルだけだとコーパスに関わる研究をしている人を批判しているように誤解されてしまうかもしれないのですが,「コーパス」の部分には他にも色々入ります。それは後ほど。
「コーパスやりたいです」が意味わからないと思うのは,コーパスは,少なくとも私の中では道具や手段だからです。もちろん,コーパスが研究の対象となることも当然あって,「コーパス言語学」という分野もあるにはあるのでそれはもちろんいいです(「んなもんはない」という人もいるかもしれないですがその戦いにはコミットしませんとりあえず)。ただ,コーパスを研究対象にするにしても,一体なんのためにコーパスを研究の対象にしていて,そのゴールは何なのかということだけは考えてほしいなと思うのです。
何か見たいものがあって,それを見るためにコーパスを用いるのがベストな選択肢であるならば,コーパスを使うべきであると思います。ただ,研究課題に対して必ずしもコーパスを用いることが適切でない場合もたくさんあります。先にコーパスから入ってしまえば,コーパスを使って研究できることしかできないわけで,最初に決めるべきは研究の対象であって使う道具ではないでしょう。これは,第二言語習得研究で使われる測定具を「◯◯やりたいです」に当てはめて考えてみればわかります。
- 文法性判断課題をやりたいです
- 視線計測をやりたいです
- 自己ペース読みをやりたいです
- 語彙性判断課題をやりたいです
- ERPをやりたいです
もちろん,測定具の妥当性を検証することという意味では,上記のやりたいことも研究になりえます。文法性判断ていうけど,一体それは何を測っているのか,測りたいものを測れるようにするためにはどんな工夫が必要なのかということは,それこそ第二言語習得研究の最初の頃から今まで続けられていますよね。これはいわゆる「テスト」も同じです。
- スピーキングテストやりたいです
- 語彙テストやりたいです
- リーディングテストやりたいです
テスト自体も研究の対象になります。スピーキングテストっていうけどそれは一体何を測定しているのか,測定しようとしているものが測れているのか,そういったことを研究課題にするのがテスティング研究者なわけです。
ですから,「測定」に興味があるのはとても良いことですし,ぜひそういう研究やってほしいなと思うのですが,「コーパスやりたいです」と言われると,「コーパス使って何をやりたいの?」と聞いてしまいます。言語教育にコーパスを応用したいということなのか(だとすればどんなことに応用したくて,それがなぜコーパスという手段なのか),言語発達をコーパスで調べたいということなのか,言語使用の特徴をコーパスで調べたいということなのか。コーパス自体が研究の目的になることって,少なくとも言語学の講座ではない場合にはそんなに多くないのではと思います。
ですから,道具立てそれ自体にこだわるよりも大事なのは,研究したいこと,明らかにしたいことを明確にすることと,それに応じて適切な道具を使いこなせるようになることです。
私は文法の習得や文処理に関心があり,そうした研究をこれまで多くやってきましたが,例えば「どんな研究をされていますか?」というような質問を受けたときに「自己ペース読み課題です」と答えることはありません。「第二言語の文法習得や文処理を心理言語学的なアプローチで研究しています。例えば,自己ペース読みなどです」と答えるでしょうおそらく。
ただし,それだけが手法ではありません。常に自分の見たいものを一番見れる方法を考えていますし,新しい実験の手法があればそれを取り入れて研究をやっていきます。興味があることもたくさんありますから,自分の興味があることに合わせて手法も選択することになります。手法が先に来てしまうと,その手法で見れることしか見ないことになり,視野が狭まってしまいます。「コーパス」という手法にとらわれて,実は自分が見ようとしていたものがコーパス以外の方法でより確実に見れることに気づくことができないかもしれません。
その意味で,道具立ての妥当性や信頼性を検証するという目的があり,そしてそれが分野にどういった貢献をするのかを理解していて,なおかつそれが自分の本当にやりたいことなのだと思えるようでなければ,手法よりも先に「見たいもの」について考え抜いて悩み抜いたほうがいいのではないのかというのが結論です。
久しぶりの更新でした。
なにをゆう たむらゆう
おしまい。